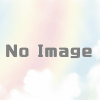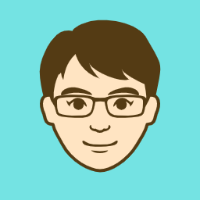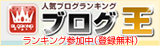正月飾り
お正月が近づくと、玄関や家の中に「正月飾り」を用意する方も多いですよね。
私の家でも、毎年、なんとなく飾ったりしているのですが、
「そういえば、正月飾りってどんな意味があるんだろう?」
と思い、少し調べてみました。
正月飾りの種類と意味
1. しめ縄
しめ縄は、神様をお迎えする、神聖な場所であることを、示すためのものだそうです。
これを玄関に飾ることで、不浄なものが家に入るのを、防ぐのだそうです。
- 豆知識: しめ縄には、藁(わら)が使われています。
これは、稲作の神様に感謝する意味もあるようです。 - 飾るタイミング: 基本的には12月28日までに飾るんですって。
29日(「苦」を連想する日)と、31日(「一夜飾り」で縁起が悪い)は、避けるのが良いそうです。
|
|
2. 門松
門松は、お正月に家に訪れる、年神様の目印になるものだそうです。
松は長寿を、竹は成長や繁栄を、象徴しているそうです。
地域によっては、梅も添えられることがあるとか。
それぞれ、縁起の良い植物です。
- 豆知識: 門松は、「神様が降りてくる依代(よりしろ)」としての役割もあるそうです。
- おすすめアレンジ: 最近は、コンパクトなサイズや、モダンなデザインの門松も、人気です。
マンションの玄関でも飾りやすいものが、たくさんあります。
|
|
3. 鏡餅
鏡餅は、丸い形が「円満」を表すそうです。
それを重ねることで「代々栄える」という意味があるそうです。
神様にお供えした後、年明けにみんなで食べることで、神様の力を分けてもらう風習があるのだとか。
- 豆知識: 鏡餅の上に載せる「橙(だいだい)」は、「代々家が続く」という願いを込めているそうです。
- 飾り方のポイント: リビングや台所に飾るだけでなく、神棚やキッチンにも、小さな鏡餅を置くと、より丁寧な印象を受けます。
|
|
正月飾りの処分方法
正月飾りは、1月15日頃の「どんど焼き」で神社に持って行って、燃やしてもらうのが、正式な処分方法だそうです。
米近くに神社がない場合は、感謝の気持ちを込めて、燃えるゴミとして処分するのも、OKだそうです。
調べてみると、正月飾りには、たくさんの意味や願いが込められていることが分かりました。
今年は、ちょっと意識しながら、飾ってみたいと思います。