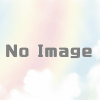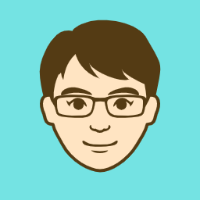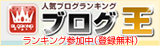寒中見舞い
今日、「寒中見舞い」という言葉を耳にしました。
「年賀状」ほど、馴染みがある言葉ではありませんよね。
でも、ちょっと気になりました。
そもそも、どんな時に送るものなのか、どう書けばいいのか、調べてみました。
寒中見舞いとは
寒中見舞いは、立春(2月4日頃)までの「寒の内」に送る、季節の挨拶状です。
冬の厳しい寒さを、お見舞いしつつ、相手の健康や近況を気遣うのが目的です。
年賀状とは少し違った、フォーマルさがあります。
送るタイミング
- 1月7日以降〜2月3日まで
松の内(1月7日)を過ぎてから、立春までが一般的な期間だそうです。
年賀状を出しそびれた場合とか、喪中の方に向けて、送ることが多いそうです。
寒中見舞いを書くときのポイント
堅苦しく考える必要はなく、心のこもった内容を伝えるのが、大切だそうです。
例文の基本構成
- 季節の挨拶
「寒さ厳しい折、いかがお過ごしでしょうか」など、冬らしい言葉を入れる。 - お見舞いの言葉
「厳しい寒さが続いておりますが、どうぞご自愛ください」など、健康を気遣う。 - 近況報告や感謝の言葉
自分の近況を軽く書いたり、お礼を述べたりする。 - 締めの言葉
「寒さが和らぐ頃、お会いできるのを楽しみにしています」など、前向きな内容で締めくくる。
どんなデザインが良い?
寒中見舞いは、年賀状ほど華やかでなくてもOKだそうです。
冬らしい落ち着いたデザインが、好まれるそうです。
- おすすめのモチーフ:
- 雪景色や椿などの冬の自然
- シンプルな和風デザイン
- 青系の淡い色調で寒さを表現
最近では、郵便局のオンラインサービスとか、アプリで、
簡単にデザインと印刷ができる、便利なツールもあります。
寒中見舞いを出すメリット
調べてみると、寒中見舞いには意外なメリットも。
- 人との繋がりを深める
年賀状の返信をしそびれた時や、久しぶりの連絡を取るきっかけになる。 - フォーマルな印象を与える
喪中の方への配慮や、ビジネスシーンでの挨拶状としても適している。 - 相手に安心感を与える
自分の体調や近況を伝えることで、相手にほっとした気持ちを与えられる。
寒中見舞いは、意外と身近で、気軽に始められるものだと感じました。
普段なかなか会えない人や、最近連絡を取っていない友人に、送ってみるのも良いですね。
デジタル全盛の今の時代に、手書きのひと言って、良いですね。
|
|